本文
夏の花々9
夏の花々9(2024)
夏の花々をご紹介します。美しい写真とすてきなエッセイをどうぞお楽しみください。
【協力:なおかつフォトエッセイ】
那智が丘にお住いのご夫婦「なお・かつ」さんが、お二人で創られたフォトエッセイです。
- かつさん(ご主人)
>>ウォーキングを楽しみながら、早朝の光の中、優しく浮かび上がる草花や自然の生き物たちを撮影しています。 - なおさん(奥様)
>>かつさんの写真に、日々、感じたこと(呟き)から生まれたエッセイを付けていらっしゃいます。
1.空木(うつぎ)
花言葉:古風・風情

ウツギは北海道から九州、奄美大島まで自生地の分布域は広く、昔は畑など耕作地の境界木としてよく植えられてきました。幹は木釘に加工されて利用されます。和名のウツギは、幹が中空であること「空木(ウツギ)」に由来しています。純白の花は「卯の花」とよばれて、古くから初夏のシンボルとして愛され、詩歌に詠まれて親しまれてきました。清少納言の随筆『枕草子』には卯の花と同じく初夏の風物詩であるホトトギスの鳴き声を聞きに行った清少納言一行が卯の花の枝を折って車に飾って帰京する話があります。近代においても唱歌『夏は来ぬ』で歌われるように初夏の風物詩とされています。
2.梅花躑躅(ばいかつつじ)
花言葉:燃える想い

このツツジは、一見して梅の花ではないかとまちがうぐらい梅の花によく似ています。ほかのツツジにくらべて、花の数が少なく、その上、新葉の下にかくれるようにひっそりと咲いています。葉は広い楕円形で、表面は光沢があり、ふちに細かい鋸歯があります。表面には毛は少ないが、裏面は細く長い毛があります。
花は7月頃に咲きますが、他のツツジとちがって、枝先の新葉の下につくので、目立ちません。枝がほっそりしているので他の木の間にまぎれこんでいるような状態に見え、目につきにくい。白い花の先は広く5枚に分れるが、赤紫色の斑点がまるく点在します。この斑点と白い花びらを遠くからみると、ウメの花のように見えるのです。
3.藪紫(やぶむらさき)
花言葉:素直になれない
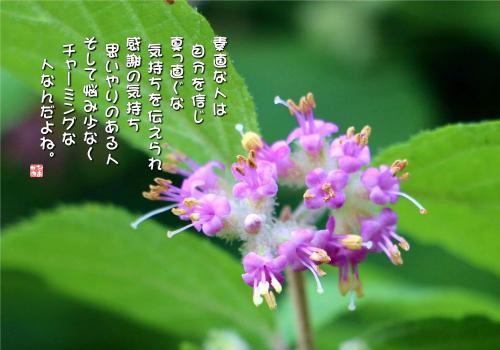
ヤブムラサキは、明るい林内や林縁部に生育しているのをたまに見かけます。
花も果実もムラサキシキブやコムラサキに似ているのですが、全体に毛が多く、葉に触るとふかふかした感じがします。ムラサキシキブに似ていて、藪の中に育つ意という説がありますが、明るい林内を好みますから、藪内には育っていないかもしれません。
ヤブムラサキは『金を集める植物』と注目されています。近年、分析技術の進歩によって、植物を用いた「植物地化学探査」が多く行われるようになっています。その過程で、ヤブムラサキが金鉱床指示植物として注目を集めるようになっています。
4.蔓黄華鬘(つるきけまん)
花言葉:心の平安

蔓黄華鬘(ツルキケマン)はケシ科キケマン属の一年草で、本州の東北地方から中部地方にかけて分布し、山地の林の中に生えます。別名を蔓華鬘(ツルケマン)と言います。草丈は数十センチですが、茎は柔らかく他の植物に寄りかかって伸びるので1メートルくらいになります。開花時期は8月から9月。葉の脇から柄を出して、緑色を帯びた黄色い花をまばらにつけます。
5.嫁菜 (よめな)
花言葉:隠された美しさ

春のころに伸びだす若芽をつんで昔から食べられていたようです。ヨメナご飯が有名です。「ヨメナ」の由来は、嫁菜とも夜目菜ともいわれはっきりしていません。オハギあるいはウハギとも呼よばれています。春菊に似た独特な香りが特徴で現在でも根強い人気があります。若葉がおいしくて、美しくやさしげな花を咲かせるため「嫁」の名をつけたとか。
6.風船蔓(ふうせんかずら)
花言葉:永遠に貴方とともに
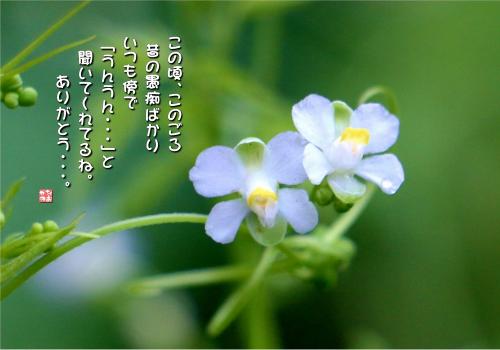
ツル性であり、周りのものに巻きつくことから「永遠にあなたと共に」という意味の花言葉が付いています。実の形から風船を連想させ、ふわふわ自由に飛んで行きそうなことからついた名と言われています。ツル性の花に共通する花言葉には「縁結び」という意味を持つ言葉もあります。どちらにしてもカップルや結婚を控えた方に贈る花にふさわしい花言葉です。成長が早く可愛らしい実もつけるので、グリーンカーテンにもお勧めです。
7.姫竜(ひめりゅう)
花言葉:深い思いやり

福玉より姫竜(ヒメリュウ)という呼ばれる方が一般的かもしれません。ヒメリュウはタマリュウの矮性種で葉は短く小さく引き締まります。淡緑の葉色がとても綺麗です。7月から8月頃に小さく白い花が咲き、12月から1月頃に小さな濃青実がなります。しかし葉の間に埋もれてあまり目立ちません。密集して植え低く密なカバーができます。地表にあたる日光を遮断しますので雑草防止や水分蒸発抑制や土の流失防止にも効果があります。和風から洋風まで幅広く合い庭造りによく使われます。
8.吾亦紅(われもこう)
花言葉:移り行く日々
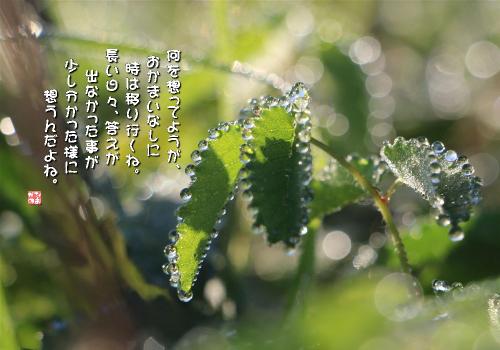
吾木香、我毛香、吾亦紅などと書き、源氏物語にも登場している由緒正しい花です。第42帖「匂宮」にいい香りのする植物の一つとして登場します。吾亦紅は食事に取り入れることができます。植物の若芽や葉は、サラダ、スープ、煮込みに加えて栄養価を高めることができます。さらに、乾燥させて風味豊かなハーブティーとして使用することもできます。わずかに苦味のある味はさまざまな料理を引き立てます。
9.露草 (つゆくさ)
花言葉:ひと時の幸せ

畑の隅や道端で見かけることの多い野草です。6から10月にかけて1センチ5ミリから2センチメートルほどの青い花をつけ、花は花弁が3枚なのですが花弁2個は大きく鮮やかな青色で、下の1枚が半透明で目立たなく、花弁は2枚のようにも見えます。朝咲いた花が昼しぼむことが朝露を連想させることから「露草」と名付けられたと言います。花の青い色素はアントシアニン系の化合物で、着いても容易に退色するという性質を持つため、染め物の下絵を描くための絵具として用いられました。
10.昼咲月見草(ひるさきつきみそう)
花言葉:奥深い愛

晩春から夏に縁に波状のぎざぎざ(鋸歯)がある葉のわきに、めしべの柱頭が十字状に裂けた淡いピンクや白の4弁花がカップ状に咲きます。花の名は、月の現れる時間に花が咲く月見草が昼間しぼむのに対して、昼間に開花することから名づけられました。乾燥したやせ地でもよく育ち、グランドカバーにも利用されます。多年草なので地下茎を伸ばして広がり、こぼれ種でもよく増えます。
11.草藤(くさふじ)
花言葉:私を支えて・儚い愛

草地や森林の日当たりの良い場所でよく見られ、日本でも一般的なマメ科の多年草です。和名は葉と花の形や色がフジに似ていることに由来しますが、フジとは異なり花穂を上に伸ばします。ハナアブが好んで蜜を吸いにやってきます。食べられる野草のひとつで、柔らかい新芽や葉を摘んで食用にでき、採取時期は東北地方以北では4月から6月ごろ。茹でてから水にさらし、和え物やおひたし、酢の物にしたり、クセはなく生のまま天ぷらやサラダの付け合わせなどにします。花の花弁だけを摘んで、軽く湯通しして酢の物にもできます。
12.藪萱草(やぶかんぞう)
花言葉:順応性

夏の盛りに野山に咲く八重咲のオレンジの野草。紡錘状に連なった根は、生薬「萱草根(かんぞうこん)」と呼ばれ、利尿、涼血、消炎、止血薬に使われます。万葉集に「萱草(わすれぐさ) わが紐(ひも)に付く 香具山(かぐやま)の故(ふ)りにし里を 忘れむがため」と謳われています。
13.吾亦紅(われもこう)
花言葉:感謝・憧れ
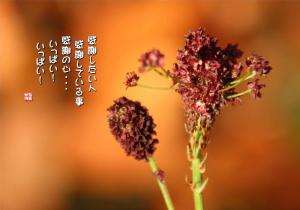
吾亦紅と書いて「ワレモコウ」と読む少し変わった印象の名前ですが、その名前は古典的な日本語で「私も赤い」という意味に由来し、多様な色と形で人々を魅了しています。名前の由来は諸説あるようです。神が赤い花を集めていた時に吾亦紅自身が「吾もまた紅なり」と唱えたという説や、中国の皇帝が吾亦紅の香りを気に入り、「吾も請う」と言ったという説があります。乾燥させても色あせないため、ドライフラワーにもよく利用されます。
14.狐大角豆(きつねのささげ)
花言葉:甘い乙女心
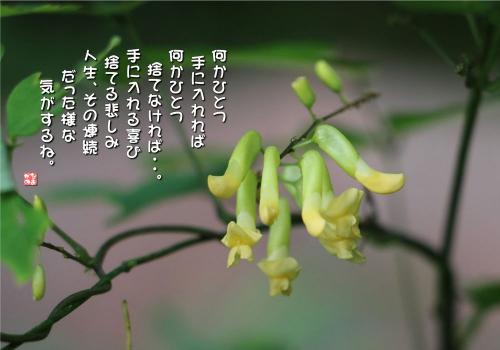
全国で、山地の林縁などに自生するつる性の多年草。名前の由来はササゲに良く似ていて狐に騙される程と言う意味で名付けられたそうで、別名をノササゲとも言います。「キツネノササゲ」とは、役に立たない(食用にならない)ササゲの意味なのでしょうか。ササゲは栽培され、赤飯や料理にも使われます。賢治作品にも度々登場します。
ほんとにささげの蔓(つる)でも頼みたいときだからな 童話「グスコンブドリの伝記」
花期は8月から9月でヤブマメの花を黄色にしたような花が咲きます。果実のさやは熟すと美しい紫色になり、乾燥すると中から青い種子が出て来ます。
15.禊萩(みそはぎ)
花言葉:切ないほどの愛・慈悲
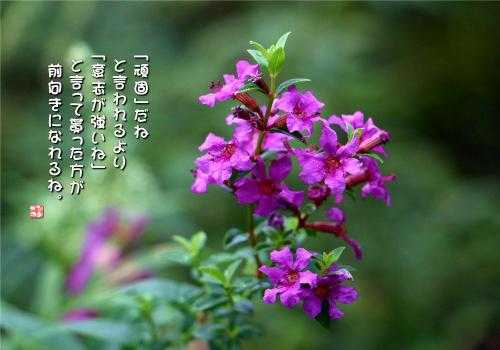
お盆に飾られるようになった理由には諸説あります。お盆に供養する餓鬼の喉の渇きを抑える作用があり、お盆に迎える仏様がミソハギの露を好むと伝えられていて、別名「禊ぎ萩」。旧暦のお盆に開花を迎えるので、水に浸しその花で玄関など周囲に水をまき、清めたうえで祖霊を迎える風習は現在でも日本各地で見られます。水路のわきや溝によく自生することから「溝萩(みぞはぎ)」といわれ、それが転じたことに由来とする説もあります。
