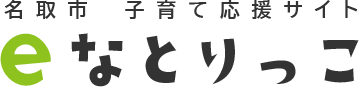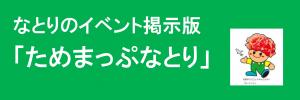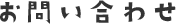本文
児童扶養手当について
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けられる方(支給要件)
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護しかつ生計を同じくする児童の母又は父(ひとり親家庭等)、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消し、父又は母と生計を同じくしていない児童
※事実上の婚姻関係(内縁の夫婦)を解消した場合も含みます。
(2)父又は母が死亡した児童
※請求者及び児童が、父又は母の遺族年金を受給している場合で、年金の月額が児童扶養手当額より高い場合は支給停止となります。
(3)父又は母が政令で定める程度の障害にある児童
※外部障害・内部疾患・精神障害等父又は母の障害の程度は定められた診断書により判定しますが、国民年金の障害基礎年金1級受給者は、診断書を省略できる場合があります。
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
※父又は母の生死が飛行機・船舶事故等により3か月以上経っても明らかでない場合です。
(5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
※父又は母が同居しないで、扶養・監護義務を全く放棄している場合であり、家庭不和や離婚を前提とした別居は該当しません。
(6)父または母がDV防止及び被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童
※父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた場合です。
(7)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
※留置所・拘置所・刑務所に継続して1年以上拘禁されている場合です。
(8)婚姻によらないで生まれた児童
※未婚で生まれた場合であり、児童の父からの認知の有無は直接関係しません。
(9)婚姻によらないで生まれた児童か不明な児童
※棄児等を養育している場合です。里親制度により委託を受けている場合は該当しません。
手当を受けられない方
- 手当を受けようとする方、対象児童が日本に住んでいないとき
- 対象児童が里親に委託されている、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき
- 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
- 対象児童が母又は父の配偶者に養育されているとき(婚姻の届はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)
支給の制限
手当額は、手当を受けようとする方、又は同居する扶養義務者の前年(1月から9月に申請する場合は前々年)の所得が一定額以上あるときは、手当の全部又は一部は支給されません。
所得制限限度額(令和6年11月から)
※受給資格者本人の所得制限限度額が、全部支給で20万円、一部支給で16万円引き上げられました。
| 扶養親族等の数 | 本 人 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
| 0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
- 受給資格者の所得(給与収入の方は給与所得控除後の金額)に養育費の8割相当額を加算した額から医療費控除・雑損控除・障害者控除等と8万円(社会保険料相当控除)を差し引いて、上表の額を比較し、「全部支給」「一部支給」「全部停止」のいずれかに決定されます。
- 扶養親族等に老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額が限度額になります。
- 本人の場合は、(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円 (2)特定扶養親族(16歳以上19歳未満)1人につき15万円
- 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(ただし、扶養親族が老人扶養親族のみの場合は2人目から加算対象)
- 扶養親族等が3人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額が限度額になります。
手当額(令和7年4月現在)
| 区分 | 児童1人の場合(月額) | 児童2人以上の場合(加算額) |
|---|---|---|
全部支給 |
46,690円 |
2人目以降 11,030円加算 |
一部支給 |
46,680円~11,010円(10円刻み) |
2人目以降 11,020円~5,520円加算 |
一部支給は所得に応じて次の算式により計算します。
児童1人の場合
手当月額=46,680円-(「受給資格者の所得額」-「全部支給の所得制限限度額」)×0.0256619
児童2人目以降の加算額
手当月額=11,020円-(「受給資格者の所得額」-「全部支給の所得制限限度額」)×0.0039568
「所得額」・・・所得(給与収入の方は給与所得控除後の金額)に養育費の8割を加算し、医療費控除・雑損控除・障害者控除等と8万円(社会保険料相当控除)を差し引いた額
「全部支給の所得制限限度額」・・・690,000円+(扶養親族等の数×380,000円)+(老人扶養者・老人控除配偶者の数×100,000円)+(特定扶養親族(16歳以上19歳未満)の数×150,000円)
手当の支給時期
手当は、認定請求書が受理された月の翌月分から支給対象となります。
奇数月の11日に前月までの2か月分が指定した金融機関の口座に振込まれます。(11日が休日に当たる場合は、その前の休日でない日が振込日となります。)
認定請求手続き
支給要件に該当し、手当を新たに受給するには、認定請求書の提出が必要です。
請求手続きには30分程度の時間を要しますので、手続きの際は時間に余裕をもって担当窓口にお越しください。
必要なもの
- 請求者および対象児童の戸籍謄本(全部事項証明書)
(離婚や死亡など支給要件が確認できるもので、交付日から1か月以内のもの) - 請求者名義の口座情報が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票など)
(同居家族全員分のマイナンバーを記入します) - 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真付きの公的な身分確認できるもの)
※その他、請求者の状況に応じて必要になる書類があります。
制度の説明も含めて、必要書類を案内しますので、認定請求を希望される方は事前に下記担当まで相談ください。
児童扶養手当と公的年金等の併給について
障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方については、令和3年3月分から児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。この改正に併せて所得の範囲が見直され、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給者の所得に、非課税公的年金給付等が含まれます。
障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金や障害厚生年金3級のみ)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合に、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
受給中の必要な手続き
現況届について
手当を引き続き受けるには、毎年8月1日時点の状況について必要書類を添えて市区町村の担当窓口に現況届を提出する必要があります。この現況届により受給資格の審査及び所得審査が行われ、その年の11月から翌年の10月分までの手当支給額等が決定されることになります。現況届が必要な方へは8月上旬までに書類を郵送しますので、内容を確認のうえ必ず期限までに提出してください。
提出が遅れた場合、本来の支給日より支給が遅れてしまう場合があります。また、2年間未提出の場合は時効により受給する権利を失いますのでご注意ください。
公的年金等を受給したとき
受給資格者、その配偶者、児童が公的年金等を受給した場合、または児童が公的年金等の加算の対象となったときは、公的年金給付等受給状況届が必要です。手当の全部または一部を受けられない場合があります。届出が遅れた場合は、手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
また、公的年金等を受給しなくなった場合、児童が公的年金等の加算対象外になった場合、その他公的年金等受給内容に変更がある場合にも届出が必要です。
住所、家庭状況などに変更が生じたとき
児童扶養手当受給資格者は、住所の変更など家庭の状況に変更が生じた場合、14日以内に居住する市区町村に届出を行う義務があります。次の事由に該当する場合は、できるだけ速やかに届出してください。
- 市内で転居もしくは市外へ転出した
- 受給者又は児童の氏名を変更した
- 新たに扶養義務者と同居になった、もしくは扶養義務者と別居になった
- 手当の対象児童と別居になった
- 所得を修正申告した(受給者・対象児童・扶養義務者の修正申告を含む)
- 受給者が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金等)や遺族補償等を受けるようになった(児童が、父母の受けている年金の加算対象になったときも含む)
受給資格がなくなる場合について
次に該当する場合は、受給資格がなくなりますので資格喪失届を速やかに提出してください。手当は資格喪失日の属する月分まで支給されます。遡って喪失となった場合、支給済の手当を返還していただくことになります。
- 受給者(父母の場合)が婚姻した、もしくは事実上の婚姻と同様の状態になった
- 支給事由が遺棄の場合、児童の父(母)親が見つかった(連絡、仕送等を含む)
- 支給事由が障害の場合、父(母)親の障害が児童扶養手当法で定められた程度より軽くなった
- 支給事由が拘禁の場合、父(母)親が拘禁解除になった(仮出所を含む)
- 児童が、児童福祉施設に入所したり、里親に委託された
- 受給者が児童の面倒をみなくなった(児童が婚姻した場合、父(母)親に引き取られた場合を含む)
- 児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった
- 外国籍の受給者・支給対象児童の、「在留期間」が切れ、「在留資格なし」の期間が発生した
- その他(児童が死亡した、日本国内に住所がなくなった場合など)
(注)対象児童が18歳年齢到達により、年度末の3月31日で自動的に支給対象ではなくなる場合、届出は必要ありません。
受給資格の辞退(辞退届)について
児童扶養手当の認定を受けているものの、手当が全額支給停止であって、今後も所得が所得制限限度額を下回る見込みがない又は公的年金等が手当額を下回る見込みがない方は、児童扶養手当の受給資格を辞退できるようになりました。辞退届の受理日が資格喪失日となります。
なお、辞退届提出後に児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は、認定請求書を再度提出する必要があります。
児童扶養手当の一部支給停止措置について
「児童扶養手当の支給を受けた父または母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない」と、法律に明記されています(児童扶養手当法第2条第2項)。
児童扶養手当は、平成14年の法改正により、離婚後等の生活の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進するという趣旨から、平成20年4月から、支給開始した月から5年または手当の支給要件に該当した月から7年(※注1)を経過したとき(※注2)は、手当額の2分の1を支給停止することとされました。
ただし、次の1~5の事由に該当する場合には、一部支給停止適用除外事由届出書(黄緑色)とその事由を証明する関係書類を提出期限までに提出することにより、5年等経過した月の翌月から翌年の10月まで、2分の1の支給停止とならずに手当を受給することができます。
その後は、現況届の際に一部支給停止適用除外事由届出書(黄緑色)とその事由を証明する関係書類を提出期限までに提出することにより、その年度の手当額(11月から翌年の10月分まで)は、2分の1の支給停止とならずに受給することができます。
対象となる方へは、事前に通知書を郵送しますので、定められた期間内に手続きをしてください。
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障害がある
- 負傷又は疾病により就業することが困難である
- 受給者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である
※注1 平成22年8月1日において手当の支給要件に該当している父については、平成22年8月1日から起算して7年
※注2 認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過したとき
児童扶養手当の適正な受給について
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進によって、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、貴重な税金をもとに支給しています。
事実婚(婚姻や同居をしていなくても、頻繁に訪問があり、生活費の援助を受けている場合などは該当)の状態にありながら届出しない、または養育費を受けていながら申告しない(過少申告する場合を含む)など、手当を不正に受給することがないよう、各種届出を適正に行っていただく必要があります。
ご自身の世帯状況が資格喪失事由に該当するかどうかの判断がつかず、受給資格の喪失が疑われる場合は、下記の問い合わせ先までご相談ください。
調査の実施について
児童扶養手当の適正な支給のため、受給資格の有無や生計維持方法等について、質問、書類の追加提出、調査を実施する場合があります。適正な支給を行うために、止むを得ずプライバシーに立ち入らざるを得ないこともありますので、ご理解とご協力をお願いします。(根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項)
手当の支払の差止について
現況届や住所の変更届など児童扶養手当法に定める必要な届出を提出しない場合は、届出が提出されるまで一時的に手当の支払を差し止めることがあります。
- 住所や氏名、手当の振込先金融機関を変更したとき
- 対象児童と別居になった
- 新たに児童が生まれたときや面倒をみなくなったとき
- 公的年金を受給できるようになったとき
- 扶養義務者と同居や別居したとき
- 所得を修正申告したとき など
※申請時と生活状況が変化したときは、下記の問い合わせ先までご相談ください。
手続きをされないまま、2年が経過すると時効により受給資格が消滅します。
(根拠法令:児童扶養手当法第15条、第28条第1項)
手当の全部又は一部を支給しないことについて
児童扶養手当法に定める下記のことに該当する場合は、手当の全部又は一部を支給しないことがあります。
- 受給資格者が正当な理由なく、職員からの質問や書類の提出に応じなかったとき
- 障害を理由に受給している場合において、医療受診を拒んだとき
- 受給資格者が児童の監護又は養育を著しく怠っているとき
- 受給資格者に正当な理由がなく、求職活動や自立を図るための活動をしなかったとき
- 受給資格者が虚偽の申請や届出をしたとき など
(根拠法令:児童扶養手当法第14条)
不正な手段で手当を受給した場合について
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、支給済の手当を返還していただくとともに、法に基づき3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
(根拠法令:児童扶養手当法第35条)
通勤定期乗車券の割引制度について
児童扶養手当の支給を受けている世帯の方々の負担を軽減するため、JRの通勤定期乗車券(運賃)の購入が3割引になる「特定者用特別割引制度」があります。